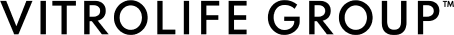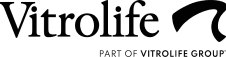人工授精は精子と卵子の受精をサポートする治療技術
近年の晩婚化に伴い、およそ5組に1組のカップルが不妊に悩んでいるとされています。
この記事では不妊治療のなかでも比較的負担が少なく、多くの方にとって始めやすい「人工授精」についてまとめてみました。
監修
山田 満稔 先生
慶應義塾大学, 医学部産婦人科学教室, 専任講師
人工授精とは一般的に、調整した精液を排卵日に合わせて子宮内へ直接注入する医療技術のことを指します。
精子の数が少なかったり運動率が低い場合に、より受精の場に近い場所に精子を入れることで受精しやすくなることを期待して行います。
精液が子宮内に入った後は、受精・着床に至るまで自然妊娠と全く変わりはありません。自然妊娠に近い治療法です。
人工授精の受精率について
年齢や健康状態によって個人差はありますが、人工授精における妊娠率は平均で5〜10%、累積妊娠率は40歳未満で約20%とされています。
1度の人工授精では結果が出ないことが多いため、多くの方が複数回行っています。
人工授精を5~6回行っても妊娠しない場合は、体外受精や腹腔鏡手術などの治療へステップアップすることを検討します。
不妊が起こる原因について
ここからは、不妊の原因と考えられている病気や症状についてご紹介します。
子宮頸管因子による不妊症
子宮頚管因子による不妊症とは、子宮頸管に起因する問題によって起こる不妊です。
子宮頚管は子宮の入り口にあたる場所です。妊娠が成立するには精子が子宮頚管を通って、排卵された卵子が待つ卵管膨大部に到達する必要があります。女性の体は、排卵日前になると頚管粘液を多量に分泌して、精子が子宮内まで到達しやすくなるよう準備をします。
このとき、さまざまな理由から頸管粘液の分泌量が増えなかったり、炎症やポリープなどの影響によって精子が子宮内に入りづらい環境であると、不妊の原因となりえます。
子宮内膜症性不妊
子宮内膜症性不妊症は、子宮内膜症を原因とする不妊です。
子宮内膜に似た組織が腹膜や卵管、腸など子宮以外の場所に発生する病気を子宮内膜症といいます。
子宮内膜症の主な症状は月経痛と不妊です。
それぞれの場所で発生した子宮内膜は月経のサイクルに沿って増殖と出血を繰り返します。本来は剥がれた子宮内膜が血液とともに排出されますが、子宮以外の場所で起こった出血はそのまま卵巣や腸の腹膜にとどまり癒着を引き起こしたりします。
溜まった血液は月経痛をはじめ排便痛や腰痛、性交痛など様々な痛みの原因となると考えられています。
子宮内膜が卵巣にできた状態を卵巣チョコレート嚢胞(のうほう)といい、症状が悪化すると卵巣機能を低下させます。
これらの結果、不妊の原因となり得ると考えられています。
卵管性不妊症
卵管性不妊症は、卵管因子によって起こる不妊です。
卵管は卵子と精子が出会い受精して再び子宮に戻るための道であり、妊娠成立における重要な役割があります。
しかし、クラミジア感染や子宮内膜症が起こると、卵管采による卵の取り込みがうまくいかなくなったり、卵管の癒着や詰まりによって卵の輸送が障害されて不妊症の原因となります。
男性不妊症
男性因子による不妊症には、精液量や精子数が少ない場合や精子の運動率が悪い場合などがあります。
原因不明不妊症
精子や子宮・卵管の状態や、ホルモン分泌や排卵の有無を調べる検査を行っても明確な原因が分からない場合を原因不明不妊症といいます。
原因不明不妊症では、加齢による卵子や精子の機能低下などが主な原因のひとつとして考えられていますが、一般的な検査では見つからない原因が潜んでいる場合もあります。
人工授精の方法について
人工授精では、まず精液を容器に採取します。
採取した精液は洗浄・濃縮してから子宮内に注入します。
人工授精のスケジュールについて
人工授精の具体的なスケジュールは以下のようになっています。
人工授精前日
超音波検査によって卵胞の大きさを確認します。卵胞の発育が得られない場合には、必要に応じて、排卵誘発剤を使用することがあります。
卵胞は直径が20㎜前後まで成長すると卵子が十分に成熟することが期待されます。排卵間近なことが確認できたら排卵を促すHCG注射を筋肉に打ちます。
HCG注射を打った翌日が排卵日となるので、排卵日に合わせて人工授精の日程を決めます。
人工授精当日
人工授精当日、男性は精液を採取します。
自宅採取もしくは採精室採取を選ぶことができるのが一般的です。
精子の調整が済んだら、人工授精を実施します。治療時間は10分前後になる場合が多いようです。
人工授精後は、感染予防のために数日の間、抗生剤を服用します。また黄体の機能が弱い方には黄体ホルモン剤が処方されることがあります。
1週間後
受精していた場合は着床の時期にあたります。
超音波検査によって排卵後の卵巣の状態や子宮内膜の厚さなどを確認したり、採血検査による黄体ホルモンの測定を行うことがあります。
注意点はありますか?
男性は2-3日の禁欲後、人工授精当日に精液の採取をすることが通常です。
3日以内の禁欲期間でもっとも妊娠率が高いとの報告がなされています。
禁欲期間が長くなると精子濃度や精液量は増加するものの、全精子運動率は低下し、30日を超えるといずれも減少もしくは低下すると報告されています。
人工授精を行う際のリスクはありますか?
人工授精時にカテーテルを使用して精液を注入する際、痛みを感じたり出血したりすることがあります。また、高熱や下腹部の痛みが現れる場合があるのもリスクの1つです。
その他に、骨盤内の感染症(0.016%(10,000周期あたり1.6件))や多胎妊娠が起こる可能性があります。
通常は子宮頚管がバリアとなっているため、精液中の細菌が子宮内へ侵入することはありませんが、人工授精の場合は精液が直接子宮内へ入ります。
子宮や卵管の中に精液中の菌が入るとお腹の中にまで達し、腹膜炎を引き起こしてしまうことがあります。
人工授精時は精液を洗浄しているため、菌はほとんど取り除かれていますが、0にすることはできません。また、腟内にもともと存在する菌が子宮内に入る場合もあります。
2人以上の子供を同時に妊娠する多胎妊娠は、排卵誘発剤を使用した場合に起こる可能性があります。
排卵誘発剤は卵胞を発育させて排卵を促す薬剤です。人工授精と併用することで妊娠率が上がります。
多胎妊娠は早産をはじめとした妊娠出産のリスクを大幅に上げてしまいます。そのため、成熟した卵胞(16㎜以上)が3個以上発育した場合には、その周期の人工授精のキャンセルが考慮されます。
人工授精の費用について
人工授精にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。一般的な費用の目安についてご紹介します。
保険は適用される?
人工授精や、人工授精の前後で実施される一般検査のいくつかの項目は、保険診療の対象になっています。
血液検査や超音波検査など、一部回数に制限がある項目もありますが、人工授精については年齢・回数の制限はありません。
人工授精の費用
人工授精1回あたりの3割負担額は5,460円。自由診療価格は30,000円前後です。
不妊検査の費用について
不妊治療の一般検査も、保険診療の対象です。子宮卵管造影検査なら3割負担額は8,000円ほどになります。
卵巣予備能を調べるAMH検査は、体外受精の場合は保険診療の対象として3割負担額は1,800円ほどとなっています。一方、人工授精を含めた一般不妊治療においてAMH検査は対象外であり、自費診療となることに注意が必要です。
まとめ:人工授精について
今回は、人工授精についてご紹介しました。
・人工授精とは、カテーテルを用いて採取した精液を子宮内に直接注入すること
・男性、女性いずれにも不妊症になる原因がある
・人工授精では、採取した精液を洗浄・濃縮してから子宮内に注入する
・人工授精は保険診療の対象となる
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考文献
- 生殖医療の必修知識. 一般社団法人日本生殖医学会 編, pp239-244, 杏林舎, 2014
- Jurema MW, et al: Effect of ejaculatory abstinence period on the pregnancy rate after intrauterine insemination. Fertil Steril 84(3): 678-81. 2005
- Dupesh S, et al: Ejaculatory abstinence in semen analysis: does it make any sense? Ther Adv Reprod Health. 14: 2020
- Matorras R, Rubio K, Iglesias M, Vara I, Expósito A. Risk of pelvic inflammatory disease after intrauterine insemination: a systematic review. Reprod Biomed Online. 2018 Feb;36(2):164-171. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.11.002. Epub 2017 Nov 24. PMID: 29287941.